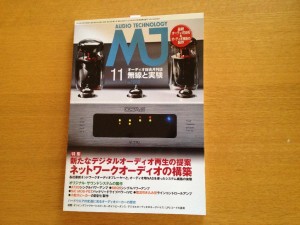ヤマハが音源ICを発表した。
http://jp.yamaha.com/news_release/2013/13102301.html
従来の音源に加えてコンサートグランドピアノCFXの音をモデルにした音源、そして初音ミクで有名なボーカロイドの音源を搭載しているという。
私は音源ICの技術が最近どうなっているか良く知らない。30年近く前にFM音源を搭載したヤマハの名機DX-7を家内が仕事で購入し私も色々と遊ばせてもらった。その頃は組み込み機器のメモリ容量が限られていたのでDX-7で採用されていたFM音源のように少ないメモリ容量で多彩な音色が出せる技術が主流であった。電子楽器としての音は魅力的であったが(フェンダーのピアノのような音など)アコースティック楽器の音とはほど遠かった。その後組み込みシステムでも大容量のメモリが使えるようになると実際の楽器の音をサンプリングしてそれを元に音を出す音源が出てきた。この頃から私はMIDI関係の技術にすっかり縁が無くなってしまった。
音声合成の世界でも最初は人間の声の発声モデル(声帯が振動して発生した信号を喉や口の特性と類似したフィルターで処理する)で発音していた。これはロボットのような声で不自然であった。しかしメモリが安価に使えるようになるとサンプリングした人の声を組合わせる音声合成システムが一般的になってきた。この方式の音声合成は違和感が無い発音が可能である。
ボーカロイドも声をサンプリングしたデータをもとに発声させる技術だ。まだ人工的な声に聞こえるが技術的には自然な発生が可能だろう。もしビジネスや法律的な課題が無ければ実在の歌手のレコード・CDをもとにその歌手の音源を作ることが可能だと思う。
楽器の音と人の声が小さなICチップに入ってしまう時代になった。そしてこれらの音をHTML5で制御する技術も標準化されているようだ。今まで遠ざかっていたこれらの技術にこれから少しずつ馴染んでいきたいと思う。
昔は夢物語だったが近い将来LPやCDに匹敵する音質を持った音源が登場して、その音源で音楽を再生することも可能だろう。いろんな楽器をサンプリングした音源をローカルに持ちコンサート会場から送られるMIDI情報で再生した音とスタジオマスタークオリティで録音再生した音の違いを判別できなくなる日が、冗談ではなく、来るかもしれない。