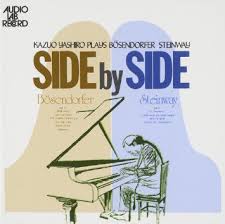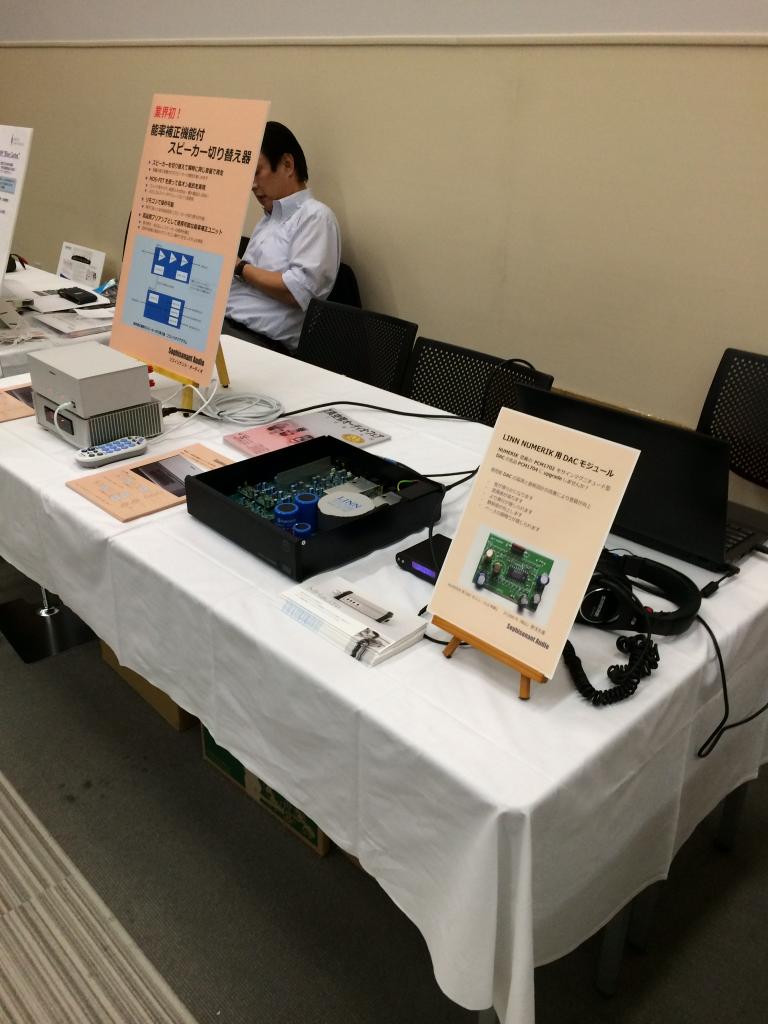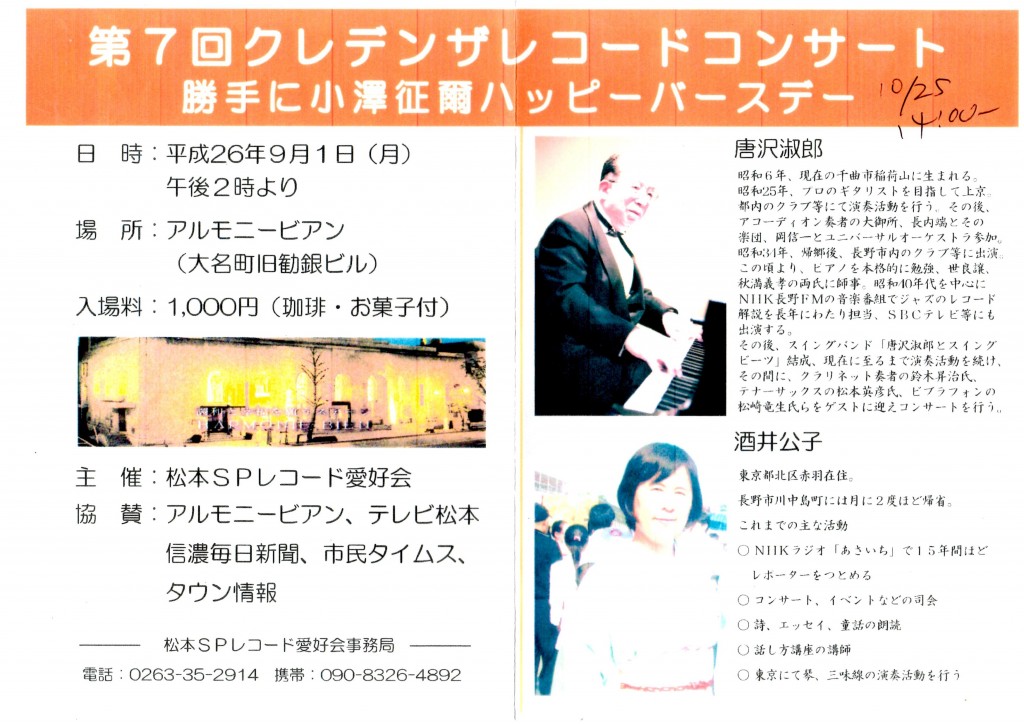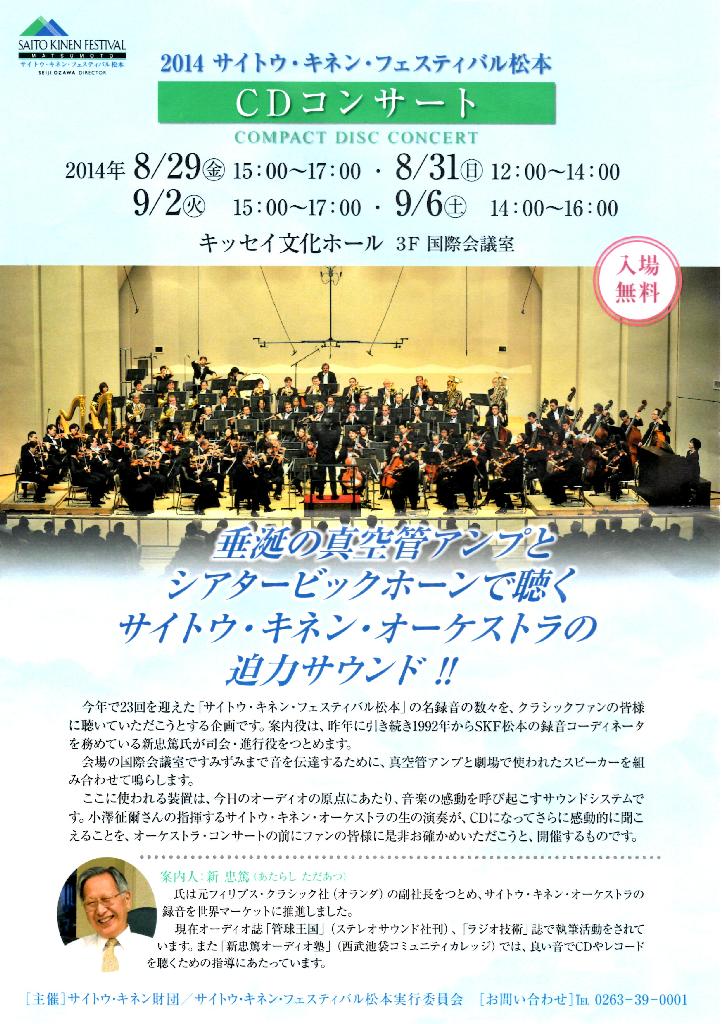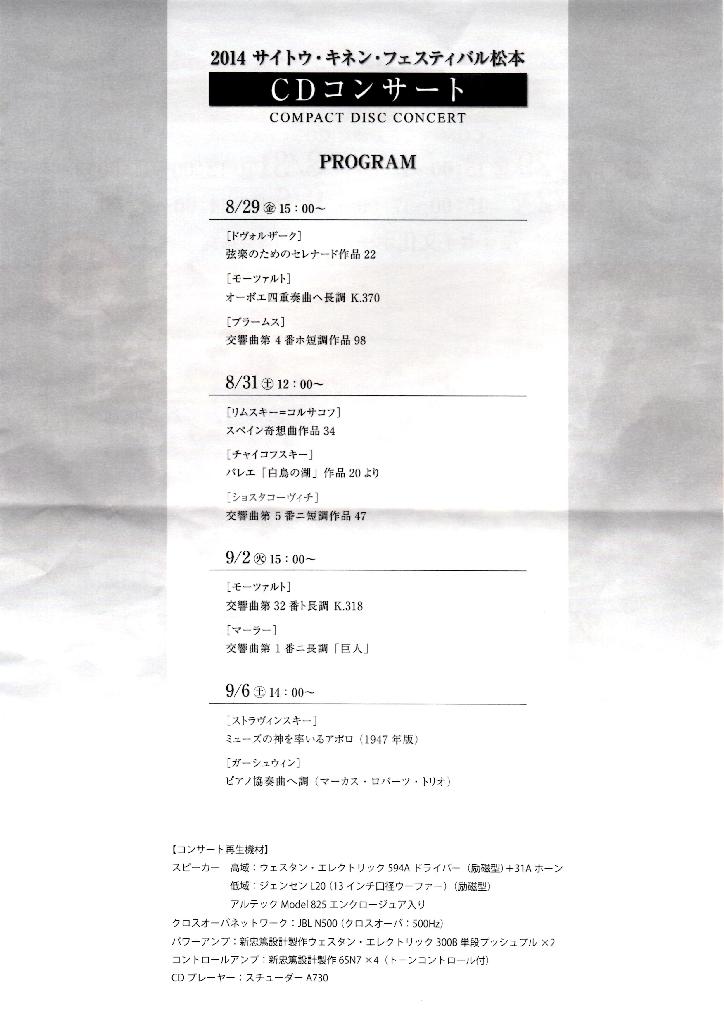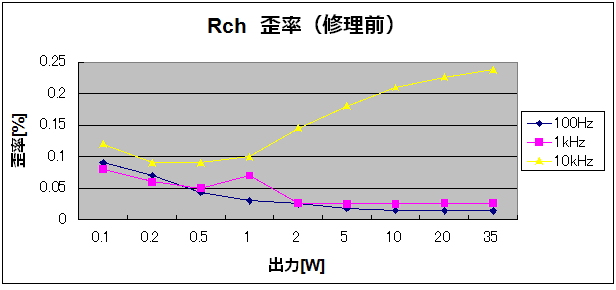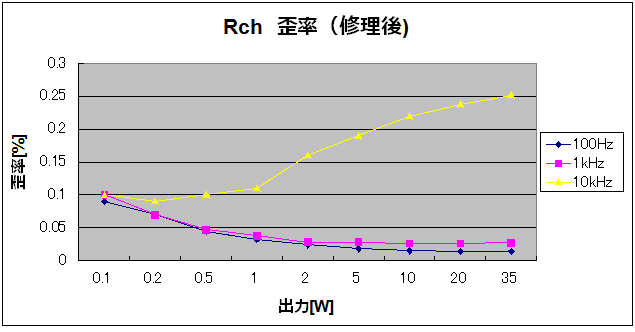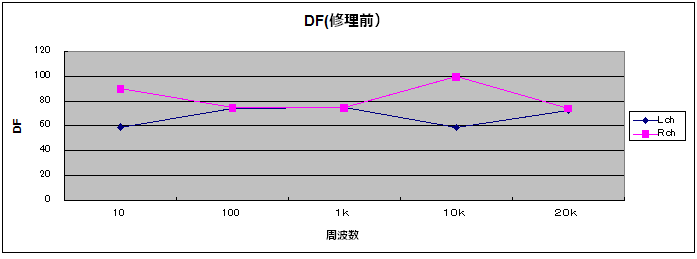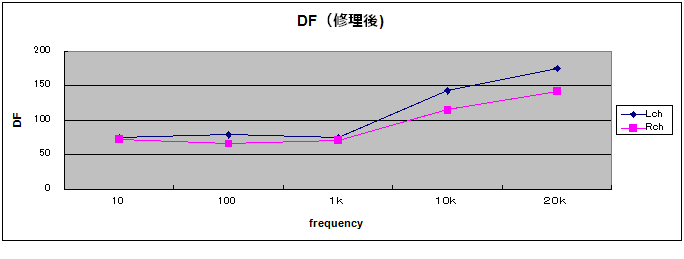5月18日、長野市芸術館にチック・コリアと小曽根真のDuoコンサートを聴きに行きました。
芸術館は5月8日に杮落としをしたばかり、ピカピカのブランニューなホールです。このホールは震災復興の影響で工数不足、東洋ゴムの免震装置の問題、そして設計ミスによって一部の席から舞台が見えないなどが原因で完成時期が1年以上遅れてしまいました。それでも今月無事オープンすることができました。
長野県内に良いホールが出来て良いコンサートが開催されるのは嬉しいことです。
チック・コリアと言えば私がJazzを聴き始めた頃、あの「Return To Forever」が発売されまさに溝が磨り減る程聴きました。それからも継続して注目しているピアニストです。一時期エレクトリックとアコースティックのアルバムを交互に出していましたが今はほぼアコースティックかなあと思います。(全部聴いていないのでわかりませんが、、)
小曽根真は何度かライブを聴いていますがあまりCDを持っていません。小曽根のスタイルは変幻自在ですが基本的にチック・コリアに似ていると思います。ビッグ・バンドを率いるなど才能溢れる演奏家だと思います。
小曽根と彼の師匠であるゲイリー・バートンとのDuoを聴きましたがそれはチック・コリアとゲイリー・バートンの演奏を彷彿とさせるものでした。二人ともバド・パウエル~ビル・エバンスから続くモダン・ジャズの主流の中に位置しています。今回のコンサートも小曽根=ゲイリー・バートンの共演と同じく師弟共演と言えると思います。
全ての演奏の曲名はわかりませんが、、以下のような演目でした。
- チックコリアのオリジナル?
- Bud Powell (アルバム Remembering Budの中の曲)
- Someone to watch over me (スタンダード)
- Spanish Song (本日のために作った曲)
- Children Song No.20
- Mozart 2台のピアノのための協奏曲 (N響と競演 7月に放映予定)
- Mirror Mirror (ゲイリー・バートンとのLPの中の曲)
- Snap Shot (小曽根のオリジナル初演)
- Fantasy for two pianos ( チック・コリアのオリジナル)
- アンコール ?
感想です。
スリリングながらリラックスした演奏で、次から次へとメロディが沸き出て来ます。お互いに刺激しあいスパイラルアップしている感じです。どちらかがアドリブを弾くともう一方がコードを弾いてバックアップしますが単純なバックでは無く相手をインスパイアーします。お互いのキャッチボールが自由自在で聴いていて本当に楽しかったです。
そして2人の演奏が非常に似ていました。手を見ないとどちらが弾いているのかわかりません。もしかしたら小曽根がチックに合わせていたかもしれません。あるいはチックが小曽根を引き込んでいたということでしょうか?
ホールの響きが良いのかピアノを強打しなくてもクリアに力強く音が響いていました。(私の席は最後部でした)音響的に優れているホールだと感じました。
ただ家内は前の席の人が邪魔でステージが見えなかったと言ってました。改修した席かどうかわかりませんが視認性には問題があるかもしれません。
いずれにしても楽しい時間をすごすことができました。
会場でチックと小曽根のDuoのCDを販売していたので買いました。このCDは過去の二人の共演のコンピレーションでした。中にはゲイリー・バートンを含めた3人の共演もあり非常に興味深いものでした。