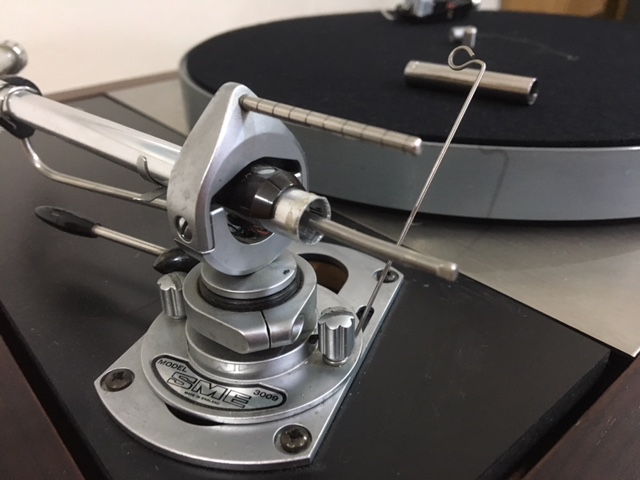昨年のことですが、Akurate DSを購入しました。
Akurate DS/K です。ライントランス内蔵の日本仕様と思ったら、UK仕様品でした。ちょっとがっかりしましたが、将来外付けトランスを追加して音の違いを確認できるのでよしとしました。
私は2008年にSneaky Music DSを購入し、その後ずっと愛用して来ました。Sneakyより上位機種がありましたが、上位機種はライン出力のみの完結したシステムでした。一方SneakyはS/PDIF出力があるので外付けDACにより発展性があり、使用するDAC次第では上位機種を凌駕できると思って購入しました。
その後10年近くほぼ毎日愛用し、無くてはならない装置です。音質は悪くは無いがすごく良いわけではないです。ハイレゾソースとCDクオリティの音質の差があまりわからないなあと思っていました。
その後、知人から情報をいただきSneakeyでは44.1kHz系と48kHz系それぞれの発振器を搭載せず100MHzから2系統のクロックを作っていることがわかりました。これが音質を悪くしていることは明らかです。発振器をひとつ減らしてもわずか数100円しかコストが減らないので、音質のヒエラルキーを作るために行ったのではないかと勘ぐりたくなります。
そこで、Sneakyに外付けDACを接続して使っていましたが、仕事中にBGMとして使用する場合などはSneaky単体使用することもありました。
Akurateは、Sneakyに比べてSN比が高く、音が滑らかでです。音の出る時、消える時の雰囲気がよくわかります。Sneakyは悪い音ではないですが、粗い感じの音です。ALTECのスピーカーのような音ともいえます。この粗い感じが良い方向に作用するソースがあることも事実ですが、、
Akurate DS/KはSneakyより2階級上で、1世代後の製品なので当然です。そして上記のようにSneakyは音質をディグレードしているので納得できてしまいます。
今回、Sneaky+DAC と Akurateの音を比較しました。
Sneaky連合軍は、Sneaky、キット屋 SV-192S そしてMUTEC MC-3です。SV-192Sはサンプル・レート・コンバータ(SRC)を搭載しているのでSneakyの意図的なジッタを除去できます。そしてクロック源MC-3を使うことで音質が向上します。SV-192SがAkurateのDACと比較してどうかという問題は残りますが、クロックジッタの影響はかなり軽減される筈なので興味深い比較です。

音源としてLinn Records の 96/24、192/24等のいわゆるハイレゾ音源を使用しました。
AkurateとSneakyで同じソースを同時に再生し、切り替えながら試聴します。切り替えながら聴くほうが比較がやりやすく、要する時間が短縮できるので楽です。
Sneaky連合軍ではいくつかの設定の選択肢があります。SRCの設定を変えればさらに組み合わせが増えますが、今回はハイレゾ音源なのでSRCの倍率はX1固定にしました。何通りもある組み合わせから以下の3通りを選んで比較しました。
設定1:S/PDIFからクロックを抽出して使用する
Sneaky単体の時と似た音がします。しかし、音の粗さが多少緩和した印象を受けます。SV-192はライン出力に真空管とトランスが入っているので音が滑らかになっているかもしれません。DACはS/PDIFからクロックを抽出するので元のジッタ残りますが、内部のPLLでジッタが多少軽減すると思います。この比較で、SneakyのDACとSV-192のDACの差がある程度推測できますがジッタ特性も変化するのでDACのみの差ではないと思います。
設定2:DAC内蔵クロックを使用する
設定1に比べて音の粗さが減りました。Akurateの音に近づいています。しかしAkurateのほうがS/N比が良く、分解能が高く感じます。 この設定ではSneakyのジッタが内部クロックによるリサンプリングでほぼ無くなるはずです。DACの音質差が聞こえると考えられます。
設定3:MUTECからクロックを供給する
Akurateとの差がわからなくなりました。SN感や肌触りの良さではAkurateのほうが優れていますが、ブラインドで聴いてどちらが鳴っているか言い当てる自信がありません。連合軍はかなり頑張っています。ちなみにMC-3からWordクロックを供給しています。10MHzを供給するシステムより低コストで高音質を得やすいと思います。
Sneakyでも外部に上質なDACを接続して適切にクロックの分離を行えば、上級機の音質に迫ることがわかりました。Sneaky購入時の考え(自分を納得させるためのこじつけ?)が正しかったことを、Akurateとの比較を通して確認することができました。SV-192Sより高音質のDACを使えばAkurateを超えることも可能かもしれません。しかしコストを考えると連合軍の構成は良いバランスだと思います。
最近は、Linn DSのような構成のネットワークプレイヤーだけでなく、DACを搭載しないネットワークプレイヤー あるいは NASからS/PDIFやUSBで信号を出力するプレイヤーなどバリエーションが増えています。それぞれ一長一短ありますが、ユーザに都合のよいシステムを構成するための選択肢が増えるのは良いことだと思います。
考えてみるとLinnは10年前にネットワークプレイヤーの形態の多様化を見越した製品を意図してかどうかわかりませんが、準備していました。買いかぶりかもしれませんが、たいしたものです。
これからもSneakyをDACなしネットワークプレイヤーとして十分活用したいと思います。